
「檀家になりたい」と考える理由は人それぞれです。
自ら望んでそう思う方もいれば、親が生前に決めていたという方もいるでしょう。檀家になる際の費用やお布施の相場、檀家としての義務や責任について気になる方も多いはずです。
檀家になる際の金銭的負担や寺院のルールは、お寺によって大きく異なります。実際に檀家になった私の体験談を参考例として紹介しますので、檀家を検討されている方はぜひご覧ください。
そもそも檀家とは何か
檀家制度の基本的な仕組みを理解することは、檀家になる前の重要な準備です。檀家とお寺の関係は、単なる宗教的なつながりだけでなく、経済的な支援関係も含んでいます。

檀家とは、特定のお寺に所属し、そのお寺の財政をお布施によって支える家のことを指します。そのお寺のことを「菩提寺(ぼだいじ)」といい、同じ意味で「お寺さん」などと呼ぶこともあります。
檀家とは、「寺院に所属する家」のことを指します。自分の家が檀家になっているのかどうかわからない、という方も多いかもしれません。簡単に見分ける方法の1つは、お墓が寺院にあるか、霊園にあるかという点です。寺院にお墓がある場合は、檀家になっている可能性が高いと言えるでしょう。
引用:全国優良石材店
檀家は葬儀・法要の一切をお寺に依頼する代わりに、お布施によって経済支援を行います。この関係のことを「檀家制度」と言います。
近年では核家族化が進み、先祖代々引き継がれてきたお墓について悩む檀家が少なくありません。また、お寺との付き合いに価値を見い出せない人も増えており、お寺との関係を解消すること(離檀)を考える人が増えています。
檀家になるメリットと問題点
「檀家離れ」が進む現代でも、檀家になることには一定のメリットがあります。一方で、経済的負担や継続的な義務といったデメリットも存在するため、両方を理解した上で判断することが重要です。

檀家になるメリット・魅力

檀家になることで得られる主なメリットは以下の通りです。精神的な安らぎや安心感が最も大きな魅力といえるでしょう。
- 宗教・宗派に従った形式的な供養を受けられる
- 没後の自分たちの居場所が確保されるという安心感を得られる
- 葬儀・法要に関して永続的に相談できる
これらの3つに共通するのは、心の安らぎを得られることです。檀家になるメリットは「精神的なものがほぼ全て」と言い換えることもできます。また、檀家になることで親や先祖に対して報いることができると考える人も多いでしょう。
檀家になるデメリット・問題点

一方で、檀家になることで生じる問題点も理解しておく必要があります。継続的な経済的負担が最も大きなデメリットといえるでしょう。
- 檀家になる際に入檀料が必要になる
- 葬儀・法要ごとのお布施、護持会費、年賀などで出費がかさむ
- 定期的な清掃活動といった、寺独自のルールに従う必要がある
- 寺を修繕したり改修する際は寄付を求められる
- 子や孫たちにとって檀家であることが負担になる可能性がある
- 離檀する際は離檀料が必要になる
すべてのお寺で上記6つが当てはまるわけではありません。しかし、大なり小なり主に経済的負担がかかることは間違いないでしょう。子や孫たちがお寺とどう付き合うかは、将来になってみないとわかりません。そのことが不安だと感じるのであれば、ずっと不安を抱えていくことにもなってしまいます。
檀家になるまでの経緯と実際の費用
実際の檀家体験談をお伝えします。私の家がどのようにして檀家になったのか、檀家になったことで費用やお布施がどうなっているかについて、具体的に説明していきます。

檀家になった経緯

檀家になったのは私の父で、タイミングは母が病気により余命宣告を受けた時でした。父は長男で実家には菩提寺がありましたが、母の実家の菩提寺(曹洞宗)の檀家になることを決断しました。
この決断には明確な理由がありました。父が実家を出て弟が家業を継いでいたこと、そして母の母(私の祖母)が健在だったことです。父は実家を継いでいないため、自分の墓をどうするかについて若い頃から考えていたようです。
- 父は実家を出ていて、弟(次男)が家と家業を継いでいたから
- 母の母(私にとっての祖母)が健在だったから
檀家になる際にかかった費用
檀家になる際に納めたお金について、私の家では次の2つの費用がかかりました。墓地使用料と戒名料が主な初期費用となります。
- 墓地使用料
- 戒名料
費用①:墓地使用料

お寺の敷地内にお墓を建てるために、400,000円を納めました。これはお墓の購入費とは別の費用です。その際に契約書を交わし、離檀する際の条件や護持会費の納付義務が明記されていました。
お墓を建てるための土地は、あくまで「借りている」ということです。護持会費を納めることも、墓地使用者の責務として契約書に記されていました。
費用②:戒名料

檀家になる際に、母の戒名の位についてお寺と話し合いました。「これから檀家になる状況なので、あまり高い位にしなくても」という考えで一致し、「清信女」という位を授かることになりました。戒名を授かるためにお金を払うというよりは、戒名の位によってお布施の金額が決まるようでした。
清信女となった母のお葬式では、以下の金額をお布施として納めました。
| 本僧(1名) | 200,000円 |
| 先僧(1名) | 65,000円 |
| 用僧(2名) | 110,000円 |
| お膳料(4名分) | 20,000円 |
| 合計 | 395,000円 |
※お葬式にはお寺の住職(本僧)の他に、他の寺院の僧侶3名も来られました。
それぞれのお布施の金額については、お寺に指示を仰ぎました。
継続的にかかるお布施や費用

父も2年程前に他界し、現在は長男である私が檀家を引き継いでいます。お寺とのお付き合いにはそれなりの費用がかかるということを事あるごとに感じます。
父のお葬式では「清信士」という位を授かり、母の時と同じ金額をお布施として納めました。その後は四十九日、初盆、一周忌と続き、先日は三回忌の法要を行いました。その都度、お布施30,000円、お膳料5,000円、合計35,000円ずつを納めました。年に1回護持会費の振り込み依頼が来るので、その都度5,000円を納めています。また、年始にはお年賀(3,000円)を持って、お寺に挨拶に伺うようにしています。
その他、檀家として必要なこと
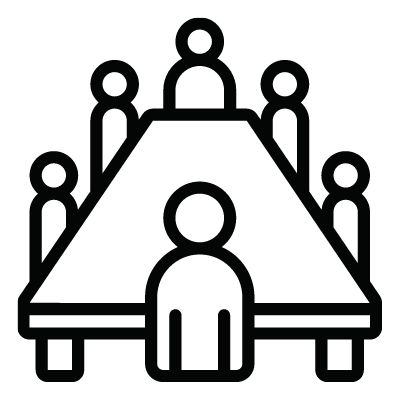
年に1回、お寺の収支報告などを行う「総会」があり、それには出席するようにしています。お寺の修繕や改修が必要な場合は寄付を求められることがあるかもしれませんが、今のところはありません。
それ以外には費用や行事的なものは特にないので、私の家の場合は比較的負担が軽い方かもしれません。お寺によって檀家の義務や負担は大きく異なることがわかります。
最後に:早めにお寺に相談することが大切
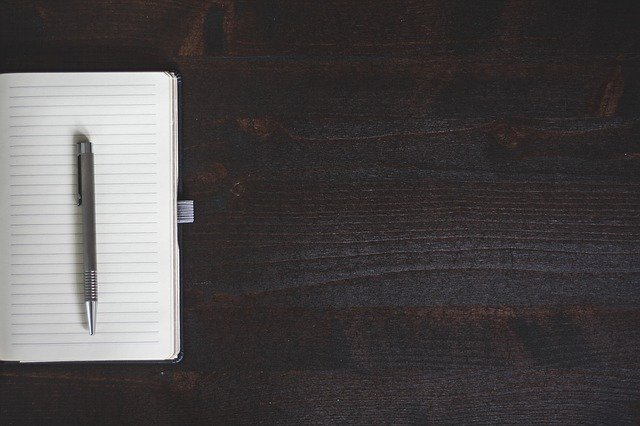
檀家になることを検討しているなら、早めにお寺に相談することが重要です。お寺ごとに決まりがあり、入檀料やお布施の金額も様々だからです。
お墓を建てたり葬儀をしたりする際に出費が重なることも多いため、早めに算段を付けておくことがとても大切です。いざという時になってからでは精神的にも追い込まれてしまうので、今すぐできることから手を付けておきましょう。檀家をどうするか決める際は、檀家の基礎知識も併せて参考にしてください。
檀家を決める他に、斎場をどうするかも決めなければいけません。詳しくはこちらの記事もご覧ください。
-

-
公営斎場と民営斎場の違いは?斎場(葬儀場)の決め方は?
「斎場の決め方のポイントを知りたい」 「斎場は公営と民営のどちらがいいのか」 このページでは、斎場を決める際のポイントや公営斎場と民営斎場の …
続きを見る

