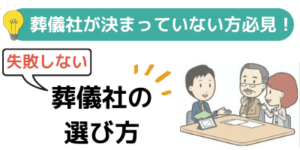はじめに:葬儀費用は工夫次第で大きく抑えられます
「急なことで、葬儀のためのお金が用意できない」「親の葬式代、一体いくらかかるのだろう…」と、葬儀の費用に関して不安を抱えていませんか。多くの方にとって、葬儀は頻繁に経験するものではないため、費用の相場がわからず戸惑うのは当然のことです。
しかし、葬儀費用は準備や選択次第で、ご自身の希望に合わせて大きく抑えることが可能です。
この記事では、葬儀費用を安く抑えるための具体的な5つの方法から、貯金がない場合でも利用できる公的な補助金制度まで、詳しく解説します。この記事を最後まで読めば、経済的な負担を軽減し、後悔なく故人様とのお別れの時間を過ごすための知識が身につくはずです。
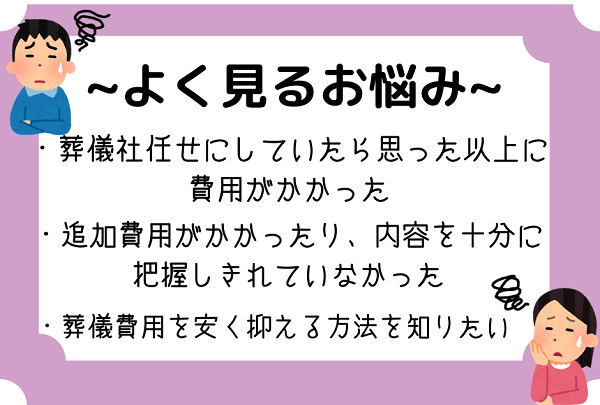
まずは知っておこう!葬儀費用の内訳と形式ごとの相場
葬儀費用を賢く抑えるためには、まず何にどれくらいのお金がかかるのかを把握することが重要です。葬儀費用の総額は、主に「葬儀一式費用」「飲食接待費」「寺院費用」の3つから成り立っています。
また、お葬式の形式によっても費用は大きく変動します。ここでは、費用の内訳と、代表的な葬儀形式ごとの費用相場について解説します。ご自身の予算や故人、遺族の希望に合った形式を選ぶための参考にしてください。
葬儀費用の3つの内訳
葬儀費用の全体像を掴むために、まずはその内訳を理解しましょう。主に以下の3つに分けられます。
- 葬儀一式費用:お葬式そのものにかかる費用です。ご遺体の搬送、安置、棺、祭壇、会場使用料、火葬料金、人件費などが含まれます。葬儀社に支払う金額の大部分を占める中心的な費用です。
- 飲食接待費:通夜振る舞いや告別式後の会食(精進落とし)といった飲食代、そして参列者への返礼品にかかる費用です。参列者の人数によって大きく変動します。
- 寺院費用:僧侶による読経や、戒名を授けてもらう際に支払うお布施などの費用です。宗派や寺院との関係性によって金額は異なりますが、感謝の気持ちとしてお渡しするものです。
これらの合計が葬儀費用の総額となります。見積もりを確認する際は、どこまでの費用がプランに含まれているかを確認することが大切です。
【形式別】葬儀費用の相場一覧
葬儀は、通夜や告別式を行う「一般葬」だけではありません。儀式の規模や内容によって様々な形式があり、選択する形式によって費用を大きく抑えることが可能です。ここでは代表的な4つの形式と、その費用相場をご紹介します。
直葬・火葬式(10万~30万円)
直葬(ちょくそう・じきそう)や火葬式は、通夜や告別式といった儀式を行わず、ごく限られた親族で火葬のみを行う最もシンプルな形式です。
儀式を省略するため祭壇や会場の準備が不要で、飲食接待費もかからないため、費用を大幅に抑えることができます。とにかく費用を安く済ませたい、無宗教なので儀式は不要と考えている方に選ばれています。
一日葬(30万~80万円)
一日葬は、通夜を行わず、告別式から火葬までを1日で執り行う形式の葬儀です。通夜振る舞いなどの飲食接待費や、遠方からの親族の宿泊費といった負担を軽減できるメリットがあります。
儀式は行いたいけれど、費用や参列者の負担はなるべく軽くしたいというニーズに応える選択肢です。ただし、菩提寺によっては通夜を省略することを認めない場合もあるため、事前の確認が必要です。
家族葬(40万~100万円)
家族葬は、家族や親しい友人など、親しい関係者のみで執り行う小規模なお葬式です。一般葬と儀式の内容は同じですが、参列者が少ないため、会場の規模を小さくでき、飲食接待費や返礼品の費用を抑えられます。
故人とゆっくりお別れの時間を過ごしたい、一般的な弔問客への対応の負担を減らしたいと考える方に適しています。近年、最も選ばれている葬儀形式のひとつです。
一般葬(100万~200万円)
一般葬は、通夜と告別式の2日間にわたって行われる、従来からある一般的な形式のお葬式です。家族や親族だけでなく、故人の友人や会社の同僚、近所の方など、生前お世話になった方々に広く参列していただきます。
多くの参列者が見込まれるため、費用は高額になる傾向がありますが、社会的な繋がりを大切にし、多くの方々と共に故人を見送りたい場合に選択されます。
【本題】葬儀費用を安く抑える具体的な方法5選
ここからは、実際に葬儀費用を安く抑えるための具体的な方法を5つご紹介します。複数の方法を組み合わせることで、さらに費用を軽減できる可能性もあります。一つひとつ検討し、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけてください。
方法1:葬儀の形式と規模を見直す(直葬・家族葬の検討)
最も効果的に費用を抑える方法は、葬儀の形式そのものを見直すことです。
前述の通り、お葬式には様々な形式があります。故人や遺族の意向を尊重しつつ、参列者を家族や親しい方に限定する「家族葬」や、儀式を簡略化する「一日葬」、火葬のみを行う「直葬」などを選択肢に入れることで、費用を大幅に削減できます。
特に直葬は、最も費用を抑えられる形式です。どのような形でお別れをしたいか、家族で話し合って決めましょう。
方法2:複数の葬儀社から見積もりを取って比較する
葬儀費用は、葬儀社によって料金体系が大きく異なります。そのため、必ず複数の葬儀社から見積もりを取り、内容を比較検討することが重要です。
1社だけの見積もりでは、その金額が適正なのか判断できません。最近ではインターネットで複数の葬儀社の一括見積もりが無料でできるサービスもあります。
見積もりを比較する際は、総額だけでなく、プランに何が含まれ、何がオプション(追加料金)になるのかを細かく確認することが納得のいく葬儀社選びの鍵となります。
比較する際のチェックポイント
複数の見積もりを比較する際は、料金の総額だけを見るのではなく、以下の点に注意して詳細を確認しましょう。
- プランに含まれる項目:棺、骨壷、遺影写真、搬送料金など、必要なものが基本料金に含まれているか。
- 追加料金の可能性:安置日数の延長、搬送距離の超過、ドライアイスの追加などで別料金が発生しないか。
- 斎場・火葬場の使用料:プラン料金に会場の使用料が含まれているか、公営斎場か民間斎場か。
- 人件費:スタッフの人数や役割に応じた費用が明確か。
- 対応の質:電話や対面での相談時に、丁寧で分かりやすい説明をしてくれるか。
これらの点をしっかり比較することで、「安いと思ったら追加料金で高額になった」というトラブルを防ぐことができます。
方法3:公的な補助金制度を最大限に活用する
実は、葬儀費用を補助してくれる公的な制度があることをご存知でしょうか。申請しなければ支給されないため、知っているかどうかで負担額が大きく変わります。ご自身が対象となる制度がないか、必ず確認しましょう。
葬祭費・埋葬料(国民健康保険・社会保険)の申請方法
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、喪主が申請することで「葬祭費」が支給されます。金額は自治体によって異なり、東京都23区は一律7万円、その他の市町村では3万円~5万円が一般的です。
一方、故人が会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、生計を維持されていた遺族が申請すると一律5万円の「埋葬料」が支給されます。どちらも申請期限は葬儀から2年以内なので、忘れずに手続きを行いましょう。
生活保護受給者向けの葬祭扶助(福祉葬)
遺族が生活保護を受けているなど、経済的に困窮していて葬儀費用を支払えない場合、「葬祭扶助制度」を利用できる可能性があります。これは生活保護法に基づき、自治体が葬儀費用を直接支払ってくれる制度です。
ただし、支給額には上限があり、原則として通夜や告別式を行わない直葬(火葬のみ)となります。利用するには、葬儀を行う前に必ず役所の福祉担当窓口に相談し、承認を得る必要があります。
自治体独自の制度(市民葬・区民葬)も確認
一部の自治体では、その地域に住む住民のために「市民葬」や「区民葬」といった独自の制度を設けています。これは、自治体と提携している葬儀社を、協定料金で利用できる制度です。
一般的な葬儀プランよりも費用が安く設定されていることが多いですが、プラン内容が非常にシンプルで、オプションを追加すると結果的に割高になるケースもあるため、利用する際は内容をよく確認することが必要です。お住まいの自治体のホームページなどで確認してみましょう。
方法4:不要なオプションやプラン内容を削る
葬儀社のプランには、様々なオプションが含まれています。故人らしさを演出するためには有効ですが、費用を抑えたい場合は、本当に必要なものを見極めることが大切です。家族で話し合い、不要なものは削るという選択も検討しましょう。
祭壇や棺のグレード
葬儀費用の中でも大きな割合を占めるのが、祭壇と棺です。祭壇は、白木祭壇や生花祭壇など種類が豊富で、規模や花の量によって金額が大きく変わります。
近年では、小規模な葬儀に合わせてシンプルな祭壇を選ぶ方や、そもそも祭壇を設けない方もいます。同様に、棺も桐のシンプルなものから彫刻が施された高額なものまで様々です。故人の人柄を思い浮かべながら、予算に合わせて見栄を張らずに選ぶことが大切です。
返礼品や会食の有無
飲食接待費も、工夫次第で大きく節約できる項目です。家族葬など参列者が少ない場合は、通夜振る舞いや精進落としといった会食の場を設けない、または仕出し弁当にするといった選択肢があります。
また、香典を辞退すれば、香典返し(返礼品)を用意する必要がなくなります。ただし、これらの対応は地域の慣習や親族の意向も関わるため、事前に相談しておくことが望ましいでしょう。
宗教儀式(お布施・戒名)の必要性を検討
寺院に支払うお布施や戒名料は、時に高額な費用となることがあります。もし故人や遺族が特定の宗派にこだわりがないのであれば、無宗教形式の葬儀を選択することで、これらの費用がかからなくなります。
また、菩提寺がある場合でも、戒名のランクにこだわらなければ費用を抑えることが可能です。ただし、菩提寺との関係性は非常にデリケートな問題ですので、一方的に決めるのではなく、事前に必ず相談するようにしましょう。
方法5:公営斎場を利用して会場費を節約する
葬儀を行う斎場には、自治体が運営する「公営斎場」と、葬儀社などが運営する「民間斎場」があります。公営斎場は、地域住民が利用する場合、民間斎場に比べて非常に安い料金で利用できるのが最大のメリットです。
火葬場が併設されていることも多く、その場合は霊柩車や移動用のマイクロバスが不要になるため、さらに費用を抑えられます。ただし、人気が高く予約が取りにくい場合があるため、早めに空き状況を確認することをおすすめします。
貯金なし・お金がない場合でも大丈夫!費用の支払い方法
「方法を工夫しても、すぐに支払えるお金がない」と悩んでいる方もいるかもしれません。しかし、諦める必要はありません。葬儀費用は、必ずしも現金一括で支払わなければならないわけではありません。
ここでは、手元にまとまったお金がない場合の支払い方法をご紹介します。
葬儀費用の分割払いやローンを利用する
葬儀社によっては、費用の分割払いや、信販会社と提携した「葬儀ローン」に対応している場合があります。クレジットカードでの支払いが可能な葬儀社も増えています。ローンを利用すれば、月々の負担を軽減しながら、きちんと葬儀を執り行うことができます。
ただし、金利が発生するため総支払額は高くなります。利用を検討する場合は、見積もりの段階で葬儀社に支払い方法について相談し、無理のない返済計画を立てましょう。
香典を葬儀費用に充てる
一般葬やある程度の規模の家族葬を行う場合、参列者からいただく香典を葬儀費用の一部に充てることも一般的です。香典の金額は故人との関係性や地域によって異なりますが、費用の大きな助けになる可能性があります。
ただし、香典はあくまで弔意としていただくものであり、金額を正確に予測することは困難です。また、香典返し(半返し~3分の1返し)の費用も考慮する必要があります。香典をあてにしすぎるのは危険ですが、支払いの一助となることは覚えておきましょう。
両親の場合→10万円〜5万円
兄弟の場合→5万円〜3万円
祖父母の場合→3万円〜1万円
その他の親族の場合→3万円〜1万円
友人の場合→1万円〜5千円
職場関係者などは5千円〜3千円
相続財産から支払う
故人に預貯金などの遺産がある場合、その相続財産から葬儀費用を支払うことが認められています。
以前は銀行口座が凍結されると遺産分割協議が終わるまで引き出せませんでしたが、現在では法改正により、他の相続人の同意がなくても一定額まで(最大150万円)であれば、葬儀費用などの目的で預貯金を引き出すことが可能になりました。
手続きの詳細は金融機関に確認が必要ですが、これも有効な支払い方法の一つです。
格安葬儀で後悔しないための注意点【トラブル回避】
インターネットなどで「総額10万円~」といった格安プランを見かけると、つい惹かれてしまいます。しかし、費用を安く抑えることだけを考えて安易に契約すると、「思わぬ追加料金が発生した」「希望したお別れができなかった」といったトラブルに繋がる可能性があります。
後悔しないために、以下の点に注意してください。
「プラン一式」に含まれる内容を細かく確認する
格安プランでは、広告に表示されている金額に、本当に必要なものが含まれていないケースがあります。例えば、ご遺体の搬送料金や安置日数、ドライアイスの費用などが「プラン外」になっており、後から追加で請求されることがあります。
契約前には必ず見積もりを取り、「プラン一式」に何が含まれ、何が含まれないのか、項目のひとつひとつを自分の目で細かく確認しましょう。疑問点は遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求める姿勢が大切です。
追加料金が発生するケースを事前に把握する
葬儀では、予測できない事態で追加料金が発生することがあります。例えば、警察の検案で時間を要し安置日数が延びた場合や、火葬場の空きがなく待機日数が長くなった場合などです。
どのような場合に追加料金が発生する可能性があるのか、その場合の料金はいくらなのかを、事前に葬儀社に確認しておくことで、不測の事態にも冷静に対応できます。誠実な葬儀社であれば、こうした可能性についてもきちんと説明してくれます。
故人や親族の意向も尊重する
費用を抑えたいという気持ちは大切ですが、喪主一人の判断で全てを決めてしまうと、他の親族とトラブルになる可能性があります。特に、葬儀の形式や規模、菩提寺との関係については、事前に家族や主な親族とよく話し合い、意向を確認しておくことが重要です。
故人が生前に「質素にしてほしい」と希望していたとしても、親族の中には「きちんとした形でお別れしたい」と考える方もいるかもしれません。皆が納得できる形を見つけることが、後悔のないお別れに繋がります。
まとめ:賢く情報を集めて後悔のないお別れを

この記事では、葬儀費用を安く抑えるための5つの具体的な方法から、お金がない場合の支払い方法、格安葬儀での注意点までを解説しました。葬儀費用は、正しい知識を持って、葬儀形式の選択や葬儀社の比較、公的制度の活用といった準備をすることで、大きく負担を軽減できます。
最も大切なのは、経済的な負担を理由にお別れを諦めるのではなく、予算の中でいかに故人を偲び、心を込めて見送るかということです。この記事で得た情報を活用し、ご自身とご家族が納得できる、後悔のないお別れを実現してください。
葬儀費用に関するよくある質問
一番安い葬儀の方法は何ですか?
通夜や告別式などの儀式を行わず、火葬のみを執り行う「直葬(ちょくそう・じきそう)」または「火葬式」が、最も費用を安く抑えられる方法です。参列者もごく近親者に限られるため、飲食接待費や返礼品も不要となり、費用総額は10万円~30万円程度が相場です。費用を最小限にしたい場合に最適な形式と言えます。
お金がない、貯金がなくてもお葬式はできますか?
はい、お金がない、貯金がなくてもお葬式をあげることは可能です。国民健康保険や社会保険から支給される「葬祭費・埋葬料」などの補助金制度を活用したり、生活保護受給者であれば「葬祭扶助制度」を利用して実質負担なく火葬を行える場合があります。また、葬儀社によっては分割払いや葬儀ローンに対応しているため、まずは役所や葬儀社に相談してみることが重要です。
葬儀費用が払えない時はどうすればいいですか?
葬儀費用がどうしても払えない場合は、いくつかの対処法があります。まずは、利用できる補助金制度がないか自治体に確認しましょう。次に、葬儀社に費用の分割払いや葬儀ローンが利用できないか相談します。故人に遺産がある場合は、相続財産からの支払いも可能です。最終手段として、生活保護の葬祭扶助制度の利用も検討されます。支払えないと一人で抱え込まず、まずは専門家や公的機関に相談してください。
葬儀費用の最低金額はいくらくらいですか?
葬儀の形式や地域、依頼する葬儀社によって大きく異なりますが、最も費用を抑えた「直葬・火葬式」の場合、最低金額の目安は10万円前後からとなります。ただし、この金額には必要最低限のものしか含まれていないことが多く、ご遺体の安置日数が延びた場合などに追加料金が発生する可能性があります。総額でいくらになるのか、見積もりでしっかり確認することが大切です。
家族葬の費用を安くするにはどうしたらいいですか?
家族葬の費用を安くするには、まず複数の葬儀社から見積もりを取って比較することが基本です。その上で、自治体が運営する「公営斎場」を利用すると会場費を大きく節約できます。また、祭壇のグレードを控えめにしたり、通夜振る舞いや精進落としといった会食を行わない、香典を辞退して返礼品をなくす、といった方法も有効です。
「小さなお葬式」はなぜ安いのですか?最低料金はいくらですか?
「小さなお葬式」が安い理由は、全国で集約した依頼を提携葬儀社に案内することで効率化を図り、インターネット中心の集客で豪華な式場や設備を持たないことで固定費を削減しているためです。火葬のみを行う最もシンプルなプランから用意されています。資料請求で割引が適用される場合があるため、公式サイトでの確認をおすすめします。
お葬式の平均費用はいくらですか?
葬儀の平均費用は、調査機関や年度によって変動しますが、近年では葬儀の小規模化が進んでいます。株式会社鎌倉新書が実施した「第5回お葬式に関する全国調査(2022年)」によると、葬儀にかかる費用の総額(飲食・返礼品・お布施等を含む)の平均は110.7万円です。内訳としては、基本料金が約67.8万円、飲食費が約19.2万円、返礼品費用が約23.7万円となっています。ただしこれはあくまで平均であり、葬儀形式によって金額は大きく異なります。